主に立ち帰る四旬節(40日+主日6日=46日)
- Fr. Simeon 後藤正史
- 2017年3月5日
- 読了時間: 3分
~真の喜びは回心・和解・ゆるしから~
四旬節(受難節:今年は3月1日、灰の水曜日から4月15日、復活祭の前日)は頑張ったり、我慢したりなどするイメージが強い季節ですが、そのようなことに力点が置かれると、本筋を見逃してしまうことになりかねません。
確かに、四旬節の間、それまでの自分を何ら反省することもなく過ごすのであれば問題です。四旬節のもともとの始まりはイエスの荒れ野での四十日間の試練に見出せます。イエスは完全な断食を進んで行い、また度重なる悪魔からの誘惑にさらされますが、ひるむことはありませんでした。この試練の四十日間を終えて、イエスは福音(喜びの訪れ)を人々に伝え始めていることに注目したい。 (マタイ4章、マルコ1章、ルカ4章)
イエスの四十日間の試練は、周囲の何ものにも屈することなく、あますところなく、ご自分の心と体を、父なる神の御意思のままに捧げることにつながる大切な期間だったと言えるでしょう。私たちは、四旬節の間、「御旨(みむね:神の御意思)のままに」生きてきたかを振り返り、神が喜ばれる、本来の自分に立ち返るよう招かれています。
わたしたちは、心と体を神からいただきました。創世記、1章、2章を時おり、読んで味わいましょう。神がお望みになられて、わたしたちが今この世にあります。しかも、「善き者」としてわたしたちをお造りになられました。このことをしっかり心に刻み、神に感謝する四十日日間でもあります。
神からいのち(心とからだ)をいただいたわたし(わたしたち)が時折、またしばしば神のもとから離れ去ってしまい、自分勝手な立居振舞をして、神や人々と真の喜びの交わりを持てなくなり、様々な隔ての壁を設けてしまいます。わたしたちは、「自旨(じむね、自己中心的な思い)」から様々なよろいかぶとを身につけ、罪や弱さのしがらみに身動きが取れない、不自由な状態になることもしばしばです。
従って、四旬節は歯を食いしばって頑張る季節と言うより、さまざまな束縛や重荷から解放されて、身軽なさわやかな原初のわたし(わたしたち)に立ち返る、ある意味、解放の静かな深い喜びに浸る季節となればよいでしょう。わたしたちの教皇フランシスコは、四旬節を「神のいつくしみを祝い、また実践するための集中期間」として過ごすこと、聖書(みことば)をしっかり黙想することを特に進めておられます。ミカ7:18~19、イザヤ58:6~11をゆっくり読んでみましょう。わたしたちは神や人と和解し、本来の自分に変えるための素晴らしい恵み、ゆるしの秘跡が与えられています。ゆるしの秘跡に進んで近づく勇気が与えられますように。
わたしも、わたしたちも神と共に生きる喜び、神にいやされる喜びを周囲の人々、出会う人々と共に分ち合うことができますように。
「主イエス・キリスト、わたしたち罪びとをあわれんでください。」
御旨のままに生涯を生き抜かれた聖母マリアのとりなしを願いましょう。
「わたしたち罪びとのために、今も死を迎える時もお祈りください。」
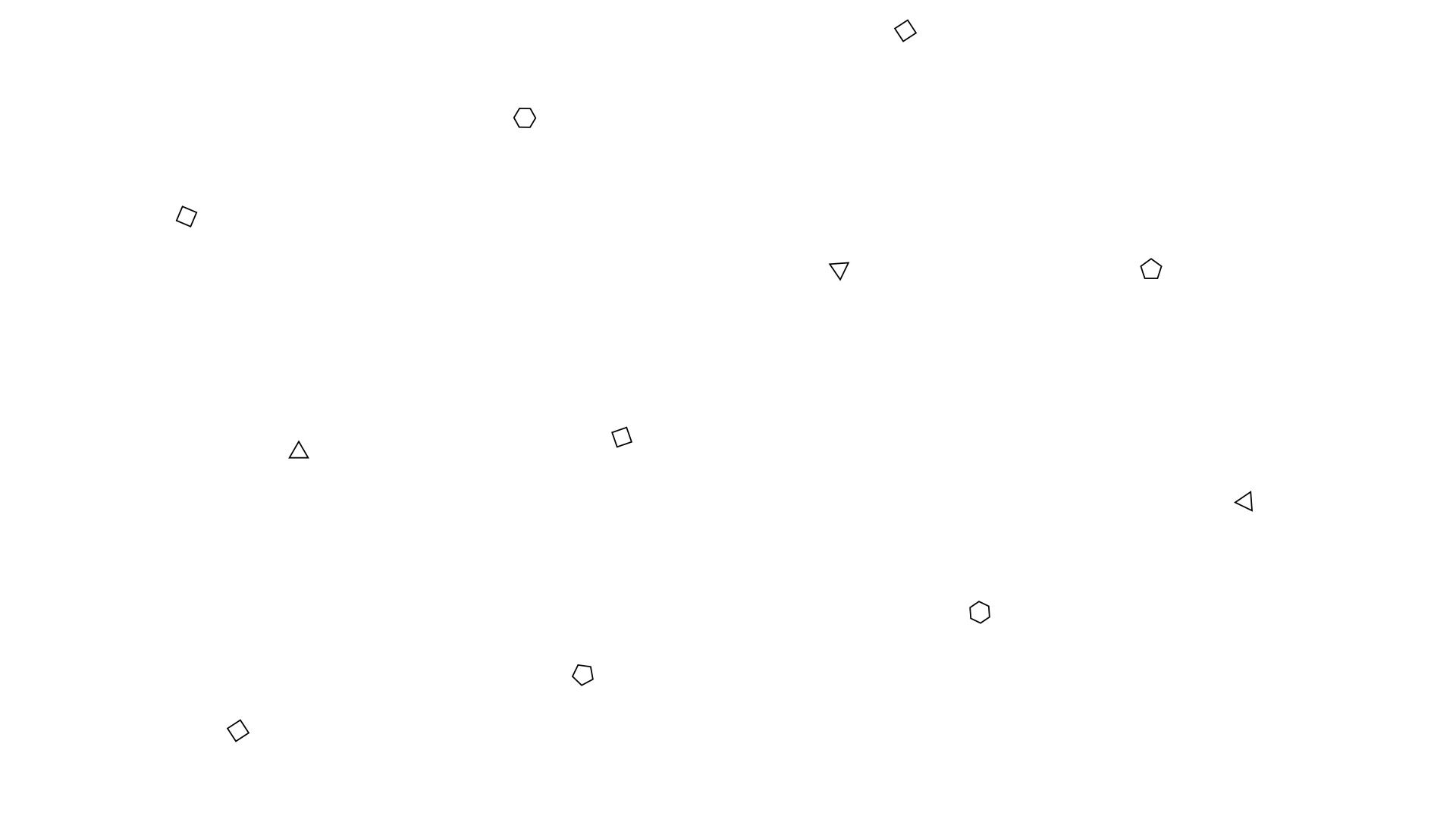


コメント